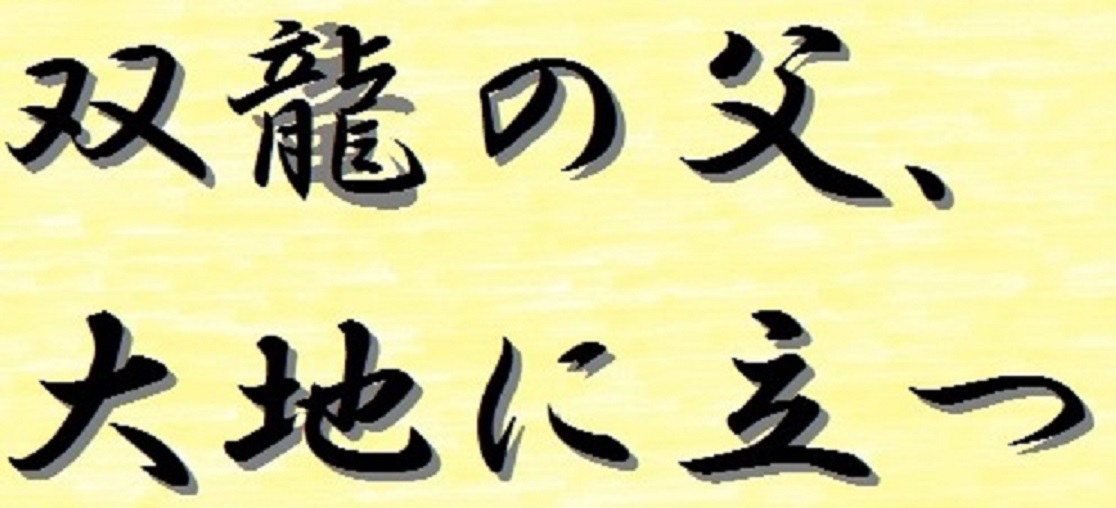自由な勉強・学びが合う子も居るが
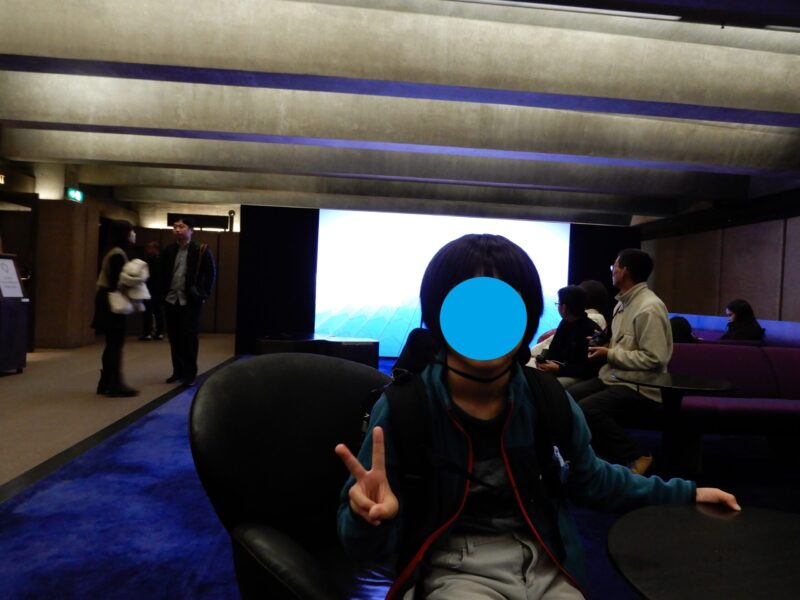
このブログは子どもたちが生まれたことを機に始めた育児ブログです。ブログを始めた当初は子どもたちが小さいこともアリ、病状だとか発育の悩みに頭を抱えていましたが、今ではそのあたりについて落ち着きを見せていて、専らの悩みは中学受験に向けた勉強になってきました。それなりに頑張っていて、頑張ったなりに結果が出ていれば程良いストレスとも言えますが、中学受験で取り組むこととなる問題は大人でも難しい内容だったりしていて、まだ 12 歳以下の小学生が挑むことを考えたら、本人の持つ才能だとか、精神的に早熟かどうかが有利・不利を分けてしまいます。才能があまり無く、精神年齢も幼い子の場合、どんなに努力してもなかなか結果に現れず…。我が家では竜太がそのクチです。
そんな竜太は自身の興味の有無でフラフラ寄り道が多いです。学校や塾、もしくは嫁さんや私のアドバイスやガイドは聞き流し、我流になったり気が向く向かないだとか好き嫌いで勉強に取り組むのでなかなか良い結果を残せずに居ます。もっと自由に好き勝手学ぶことが出来ると良いのですが…。
スポンサーリンク
受験科目は自分のルールではない
本来、人間が学ぶことというのは自身の経験からだったり、興味を持つような内容を掘り下げて未知の領域に発見を見い出したりといったアプローチだったはずです。その意味においては、竜太の興味の有無や好き嫌いで取り組もうとする勉強方法はそう間違っていないはずです。
がしかし、勉強の成果で学校の合否が決まるようなケースにおいては別の話です。出題するのは学校側です。学校が多くの受験者をふるいにかけて絞り込み、優秀な子のみに合格を与える仕組み。なので必要な勉強を定義するのは学校側なのです。その学校に行きたいのであれば、その定義に従って勉強する必要があります。また、そういった勉強はアカデミックに教科として確立されています。なので、自身のルールを当てはめるような隙は無いのです。
自然法則ですら自分のルールではない
受験においては自身のルールではないことは前述の通りですが、では興味ある内容を探求心を持って掘り下げて勉強する場合はどうなのか。勿論、勉強する対象は自由に選ぶことが出来るかもしれません。また、アプローチも色々と自身の考えで決めることも出来るかもしれません。がしかし、勉強を重ねて研究を続けると、対象のモノゴトには何かしらの法則があることに気付くでしょう。その法則を知り、まだ見ぬ新たな法則を発見していくことが学びだったりしますので、やはり自らルールだとか法則を作るようなことでは無いのです。
こんな風に考えると物事を学ぶということは身勝手な振る舞いでは成し得ず、ルールや法則に自身を合わせる必要があることが分かります。自由にノビノビと好き勝手試して調べて勉強したいと言う人も居ると思いますが、最後に行きつくところはやはり自身では抗えないルールや法則です。何事もそれを踏まえての取り組みです。守破離の基本は守です。ここでしっかりとルールや法則を学び、それがあっての自分流だとかまだ見ぬ道を見つけるようなアプローチなのです。