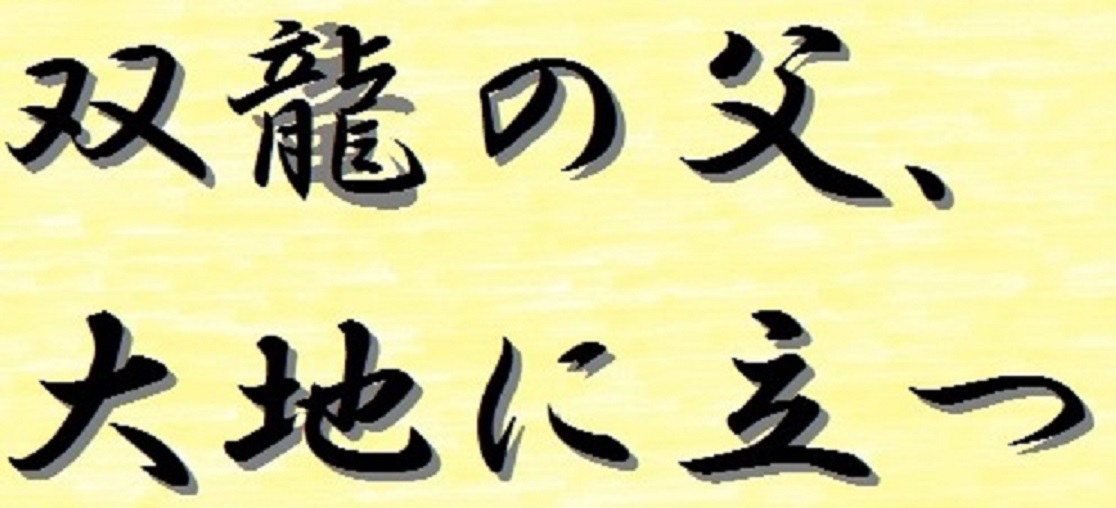宿題という扱いが苦手

このブログは子どもたちとの育児生活を中心に綴った育児ブログです。子どもたちのコトで最近の悩みのタネは専ら、子どもたちの勉強と学力になって来ました。普通にしていれば、小学生のそんなことに気を揉むことも無く、それよりも心の成長だとか習い事だとか、もしくは躾だったり一般常識といった生活態度だったり、そんなことに悩む方が健全と思いますが、加熱されている中学受験の熱だとか入試問題の難化を背景に、そこに挑む上で子どもたちは小学生らしからぬ重荷を背負っています。確かに小学校での履修範囲とはいえ、国語の読解問題の文量は半端ないですし、算数の問題も初見での閃きを必要とするような大学受験のような感覚だったり、理科や社会においては暗記するだけでは通用しないような問題解決能力を試さりたりだとか、本当に常軌を逸する内容になっています。
が、まだまだ小学生なので、家での勉強の一部に “宿題” として課せられる取り組みがあります。がしかしこの宿題、非常に扱いが面倒に思えます。
スポンサーリンク
宿題の存在が色々と錯覚
宿題は学校やら塾の授業を踏まえ、家で取り組む勉強であって、基本的には取り組んだ結果を先生に提出する流れになっています。宿題 = 家出の勉強 という捉え方が一般的なのか、宿題を終えたらもう勉強しなくても良いような感覚があります。宿題さえしておけば、家での勉強は十分、といった錯覚さえも。ところが、与えられた宿題をするだけではテストの結果もイマイチになりますし、ましてや入試に向けて宿題だけで十分かと言うとそんなこともありません。
それでは宿題は一体何のためにあるのか。勿論それは通っている学校やら塾次第なので、一概に言い難いモノがありますが、概ね、通っている学校やら塾の平均的なレベルの人たちが最低限取り組むべき勉強、といった位置付けに考えるのが差し当たりないように思えています。
テストに関係する宿題とそうでない宿題と
受験に向けて勉強している場合、合格を目指して勉強しています。その合格に向けて勉強する際、ある程度の範囲でテストを受けたりします。習熟度だとか定着度だとかを測ったり、弱点を見つけたりするために。合格というゴールまでの道のりの中に各種試験があり、一つ一つの試験だとかそれに向けた勉強が蓄積されて、最後には試験本番で戦うための武器となります。
このように考えると、受験を経ての合格を狙っている以上、宿題なんてものはなくとも自ずと取り組めそうに思えます。それでもなぜか出題される宿題。宿題がテスト勉強も兼ねているなら良いのですが、宿題はテスト勉強のほんの一部でしか無かったり、例えば夏休みの宿題には多岐に渡った取り組みとかもあるのでテストには関係しないようなモノもあったりします。とは言え宿題なので提出しなくてはいけなく、提出するためにも終わらせる必要がある…。スケジュールする際、テスト勉強の一部となっている宿題とそうでないモノを切り分けて、取り組むタイミングだとか他のテスト勉強を加味してペース配分を考えて、と色々と厄介です。