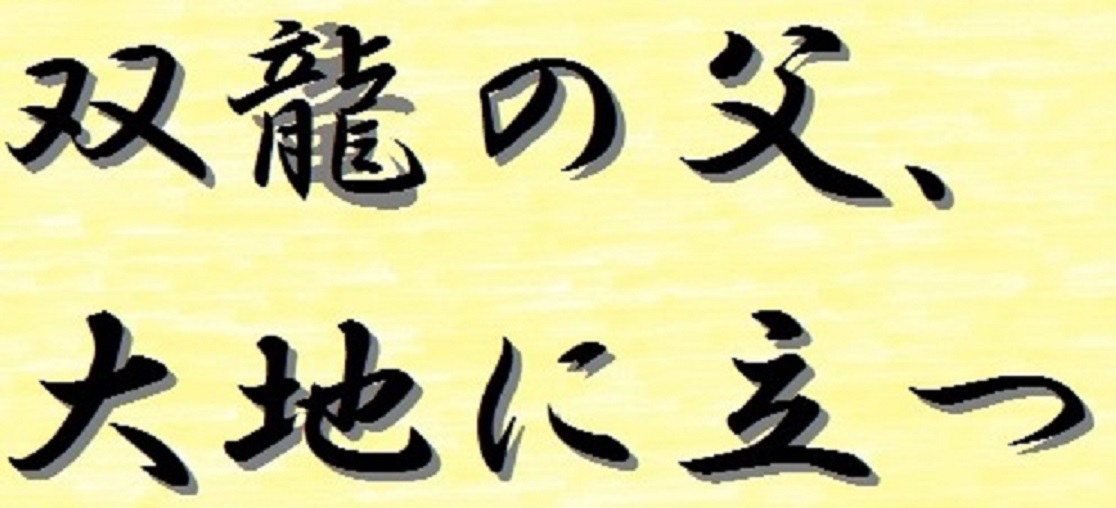作業にせずポイントを意識
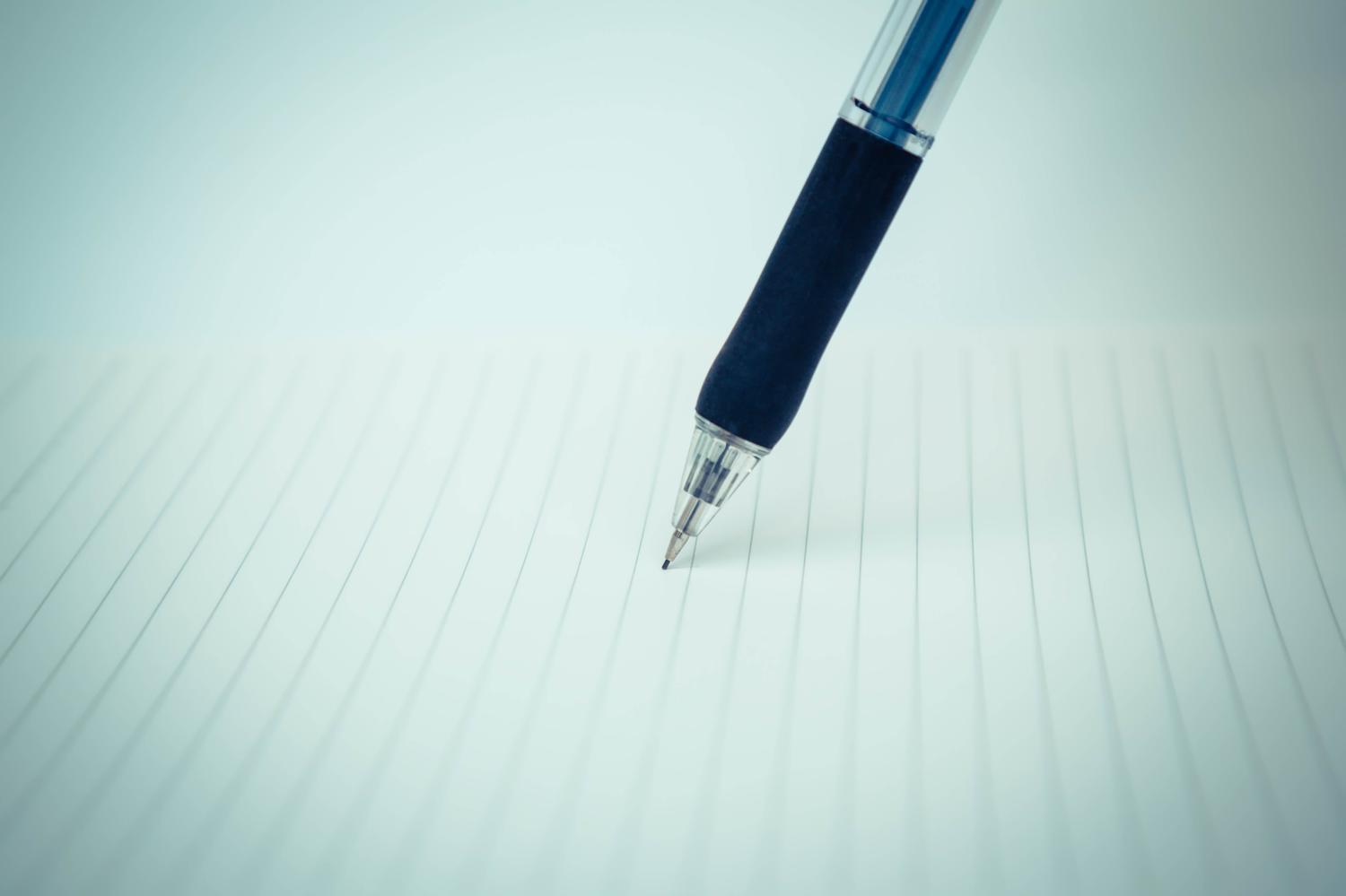
このブログは子どもたちが生まれることを機に始めた育児ブログです。子どもたちももう小学 4 年生で随分と体調は安定しています。保育園に通っていた頃の、熱や下痢で保育園から連絡を受けて速攻で仕事を早退してお迎えに行くような生活をしていたのが嘘のようです。その頃の想定では、子どもたちが 9-10 歳になる頃にはお友だちと勝手に遊んでもう親の私なんて相手にしてくれないのかと思っていました。がしかし、中学受験に向けた勉強に取り組んでいることもあり、親子二人三脚状態。まだまだ子どもたちとは多くの時間で関わっていますが、恐らくこれが最後の共同の取り組みになるでしょうね。
中学受験の要は算数と聞きます。子どもたちが通う塾でもその方針。そのため、我が家でも算数の勉強時間や回数が多いのですが、定着が甘い内容は反復練習して復習します。必要なコトなのですが、これをすると答えを覚えてしまって解けた気になり錯覚してしまうことが悩みどころです。
スポンサーリンク
記憶で解く罠
子どもたちの通う塾でも、算数の問題の反復練習が推奨されています。一方、国語の読解文は繰り返し練習してもあまり効果が薄いからか、あまり解き直しだとか復習を促されません。実際に読解問題については答えを知ってしまって解くと何の難しさも無く何の練習なのか分からなくなる感じがします。算数についても解法や答えを覚えてしまっていては繰り返し練習してもただの作業になってしまいます。が、まだまだ定着していないような問題であれば細部まで覚えている訳では無く基本的な解法を思い出したり思い付いたり出来るか試せるので有益に思えます。
竜子は記憶力が良いためか、算数の繰り返し練習をするとどんどんスラスラ解けるようになっていきます。それである程度の習得には至っているので文句がある訳では無いのですが、そこまでスラスラ解ける割には相変わらず初見の少し難度が高い問題となると手が止まってしまうようです。やはり記憶に頼って算数を練習していると、既知の問題に強くなるものの、初見で発想力を試されるような問題にはなかなか歯が立ちませんね。
ポイントを自分で意識できるか否か
では覚えてしまった問題を解くこと自体に意味がないかというとそうでもないと思います。そこまで定着した問題であれば、その問題を解く上で何がポイントなのか見えて来ているはずです。問題を解く際、ここがポイントだぞ、と思ったり、まだわかっていない他者に説明・解説するような気持ちで問題に挑むと他の問題にも通用するような経験値に昇華することが出来ると思います。
算数や数学でいつも心落ち着かないのは初見の問題で解法が思い浮かばないときです。出題側も取り組み側の攻略を踏まえていますので、まだ見ぬ形での出題を考えます。が、そういった初見の問題であったとしても、実は肝だとかポイントとなるところは既出の問題と共通だったりします。そこを普段から意識して抑え、まだ見ぬ問題でも気を付けたり注意する点だと頭に刷り込ませながら、普段の問題の演習に挑むと良いのですが、うちの子どもたちにそれが出来るのか否か…。