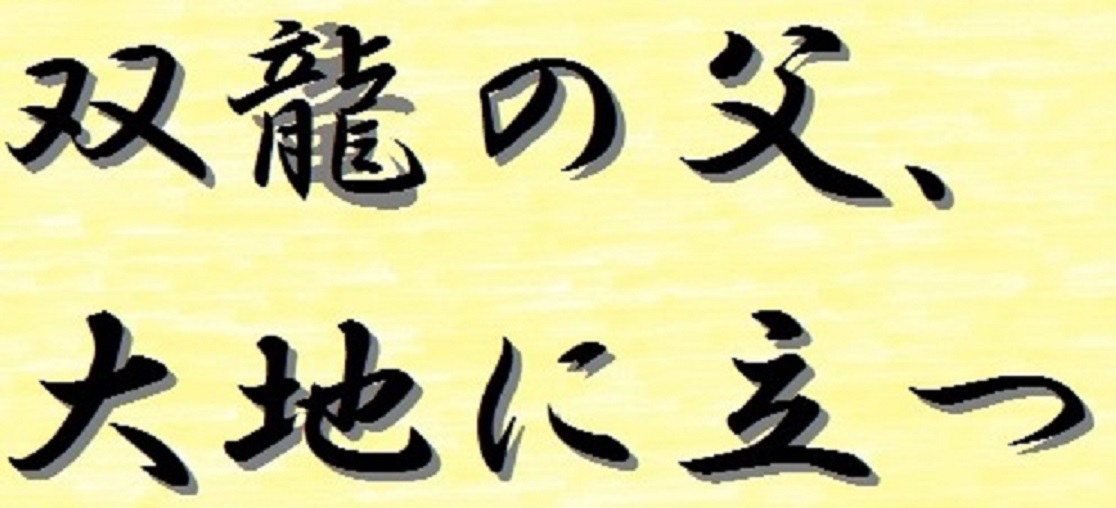算数の問題の共通項や本質を学べるか否か

このブログは主に子どもたちとの生活を綴った育児ブログです。保育園時代は主に子どもたちの病状や成長に悩む日々でしたが、今では子どもたちの学習面が悩みのタネになりました。それだけ子どもたちはしっかり成長して大きくなったということだと思います。
そして最近の悩みのタネの更に中心は、中学受験に向けた勉強についてです。学校の試験よりも高いレベルを求められる塾の試験結果に一喜一憂。まだ小学 4 年生でこれです。このままでは小学 6 年生まで私の心と体が持たなさそうです。
弱音を吐いていても仕方が無いので、少しずつ肩の力を抜こうと努力していますが、同時に諦めに似た感覚も芽生えます。子どもたちの普段の勉強ぶりと結果が伴わない感じを見ると、才能面で無理があるのかもしれません。特に算数については…。
スポンサーリンク
繰り返し練習で体得するモノ
算数の勉強は反復練習が基本です。初見でどこまで解けるのか、という発想力も最終的には勿論必要になりますが、その発想力も基本が身についていないと養えません。うちの子どもたちが通う塾でも、同じ問題の解き直しだとか復習をするように指導されています。その繰り返しの練習の中で段々と算数的な要素の本質が見えてきて、少しくらい問題がアレンジされても正答を導き出せるようになるのですが、これをうちの子どもたちが体得するのは非常に困難に思えています。
勿論、何とかそういうエッセンスみたいなところは塾の先生は勿論のこと、私からも説明していますが、子どもたちに上手く伝わっているのか否か、非常に懐疑的です。なぜなら、塾のテストで問題が少しアレンジされると途端に誤答が増えるので…。うちの子どもたちが家であれ程解き直しや復習をスラスラ出来るようになっているのに、なぜ類似問題が解けないのか。やはり子どもたちにはまだ本質みたいなモノが見えてないように思えます。
自力で見出すしか無いのか
子どもたちが解き直しや復習で同じ問題に取り組む際、多分、心構えが不十分なのだと思います。ただただ淡々と該当の問題の記憶で解いていて、算数的な要素となる仕組み部分に頭が回っていないのだと思います。問題で問われていることは何か考えて、それに合わせた式を作り、問題文と照らし合わせて自身の思いついた解法が適してそうか確認しながら解くような心構えが無いと、なかなか問題で学ぶべき本質理解までには辿り着かない気がします。
とは言え、細かく問題をアレンジして出題するのもオペレーション上、無理があります。何とか子どもたちには繰り返し問題に取り組むのことで見えて来る本質があるのことに気が付いて欲しいのですが、果たして…。