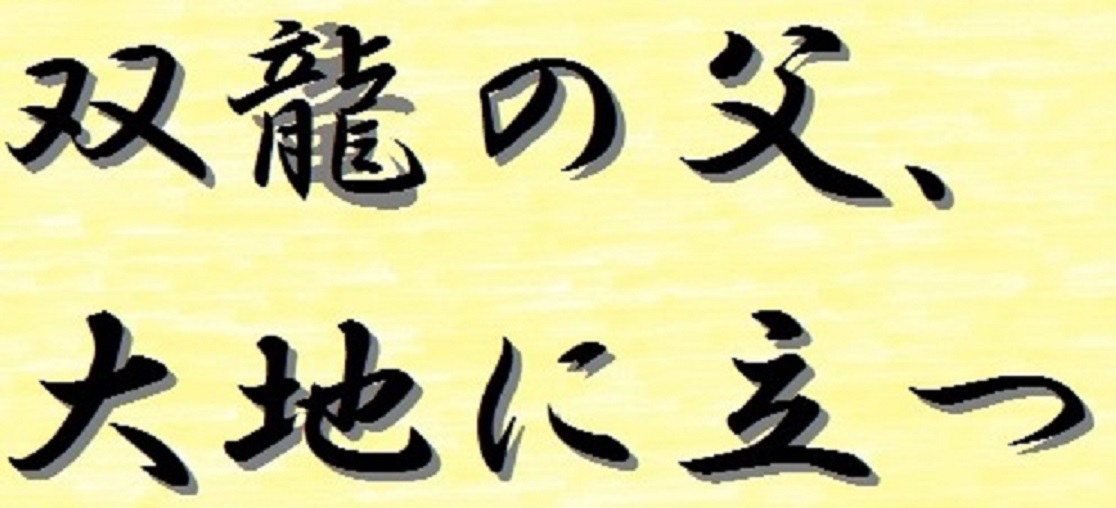実は親も勉強になる子どもたちの勉強支援

このブログでは何度も触れていますが、うちの子どもたちは毎日コツコツと勉強に取り組んでいてとても偉いです。才能が無い故か、残念ながらその努力が報われる程の結果が出ないところが可哀相に思えています。才能の有無は親の遺伝に関わるところと思いますので、そんなことにも責任を感じてしまいます…。申し訳なさでいっぱいです。
その穴埋めと言う訳では無いのですが、子どもたちの勉強をこれまでずっとサポートして来ました。そしてふと気づいたのですが、この 1 年くらいで、この子どもたちの勉強を通じて自身も勉強になっているケースもあったりします。
スポンサーリンク
使いこなせていなかった英文法
子どもたちの勉強の取り組みの一つに英検の勉強があります。私が高校を卒業するタイミングでは、私が英語を誰かに教えていることなんて想像も出来ませんでした。全教科の中で英語が一番苦手で嫌いだったからです。大学を卒業してから英語を遠ざけて逃げて来ていましたが、15 年前あたりから英語の勉強を再開。今まで継続して来ましたが、ある程度上達したものの、その後はずっと鳴かず飛ばず。それでも継続し続けていますが、それが功を奏したのか、子どもたちが自分たちも英語を勉強したいと興味を持ってくれたり、私が英語を子どもたちに教えることに繋がっています。私に英語の才能があって、一足飛びに上達してしまっていたとしたら、こういった事象は生まれなったように思えます。
で、子どもたちは先日、英検 4 級を合格していますので、今は英検 3 級に向けて勉強中。文法を教えるのは私。その際、自分自身が英会話レッスンで使っていなかった文法の再発見があったりします。例えば when to V (動詞) だったり what to V (動詞) です。そういえばそんな表現もあったな、と再発見。英会話で使って自身にも再定着させたいと思ってしまいました。
思考力強化の問題
また、子どもたちが通う塾では 3 年生カリキュラム終了時まで、思考力強化の宿題をメインで扱っていました。こういった問題、大人は中学や高校の数学の知識で解いてしまい勝ちですが、それを封じて小学生の小 3 までの知識で解こうとするとなかなか工夫と発想力が必要となります。ある程度解けるのですが、中にはすぐに解法を思い付けないモノもあったりしました。子どもたちが躓いているところに程良いヒントを出すためにも、そういった難しい問題は私が先行して解法を見つけておくような取り組みを繰り返していました。
子どもたちはその取り組みを通じて上達していますが、並行して私自身もそういった問題に解き慣れて行き、問題が求めるような発想力を身に付けて来た気がします。その結果、難しい問題であっても凡そのアタリが付くようになり、問題を解くのに時間を要しなくなりました。私自身、成長してしまったようです。育児・教育を通じて自身も成長する。よく言われていることですが、学問についても同様とは思いもしませんでした。