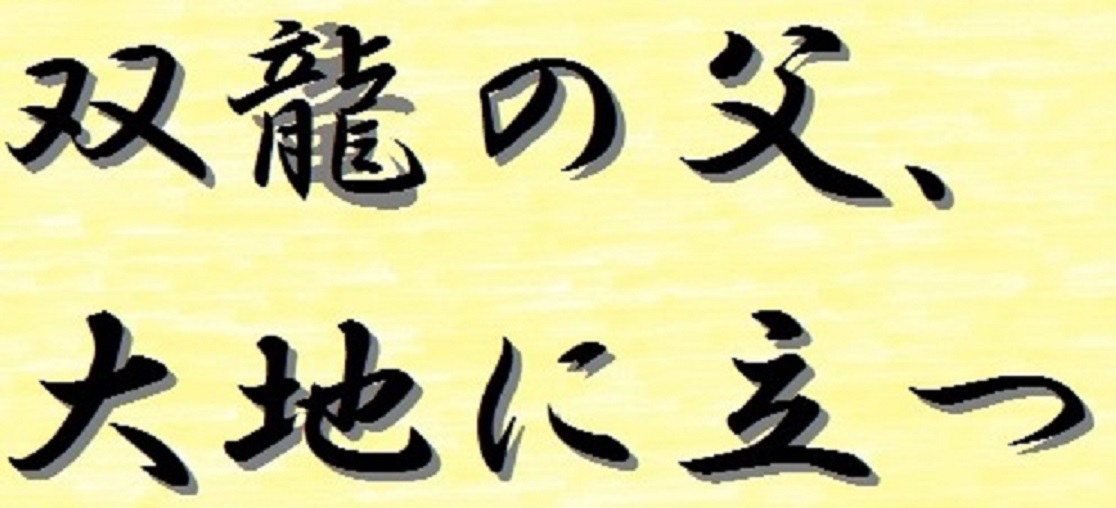倍数・約数の問題は大人も難しい

このブログでは何度も触れていますが、うちの子どもたち、毎日コツコツと勉強に励んでいます。がしかし、学年が上がるにつれて、同学年の子たちも勉強に力を入れ始めていますし、小学 4 年生なので中学受験に向けた勉強ももう本格化しています。同学年の子たちも随分と本腰なので、子どもたちのこれまでの頑張りも掻き消す勢いで、見事に一蹴されている気がします。子どもたちはこれまで頑張って来たのに、塾のテストでは平均くらいと平均から随分と下の方という辛い結果となりました。
だからと言って取り組みが変わる訳では無く、淡々とコツコツと頑張るしかありません。最近、子どもたちは苦手な倍数・約数の問題に取り組んだのですが、やはりこれ、難しいですね。
スポンサーリンク
各種の値の意味合い
算数・数学で大切なのは計算出来ることではありません。勿論それは大切ですし、むしろ必須だったりしますが、それはただの筋トレ的なモノでしかなく、淡々と鍛えて行けば上達する類です。その一方、伸ばすのが難しいのが数学的なセンスというか、式や値の意味合いを理解しなければ解けないような問題は結構大変です。図形問題のようなセンスとも違い、数字と言う抽象的な情報をロジカルに扱う必要があります。
例えば、割り算の意味合いだとか、計算結果となる商や余りの意味合いや、掛け算や割り算で実は内包されているような倍数・約数の意味合いだとか。こういった計算を扱う問題は結構難しいです。どういう計算式を立てて解けば良いのか、かなり迷子になってしまいます。
ひたすらコツコツと
取っ付き難い問題であっても、基本を理解してひたすらコツコツと何度も練習するしかありません。それは練習を通じて前述のような式だとか各種の意味合いの理解を深めることが目的です。各種問題の答えと解法を覚えているかどうかを試すようなアプローチではさっぱり上達しません。その解法が基づく考え方を咀嚼して腹落ちさせることが目的となります。
がしかし、そういった更に抽象的な学習概念を小学 4 年生が理解出来る訳も無いので、繰り返し練習する中で何かを見い出してもらうしかありません。これは子どもたちの勉強をサポートする大人も骨の折れる取り組みとなります。ただ答えが合っているから丸をするのではなく、どのようなアプローチで解いたのか確認したり、少し難しい問題に挑戦させるとやはり手が止まってしまうところ、適切なアドバイスやヒントをあげたり、と。極めつけは大人が見ても分からないような問題があったりして、更に厄介な場合はその問題の解説を読んでもさっぱり分からないことすら多々あります。
現在、子どもたちは小学 4 年生。更に学年が進んで、更に難しい問題を扱うようになると、もう私でも解説不可能になるかもしれません…。